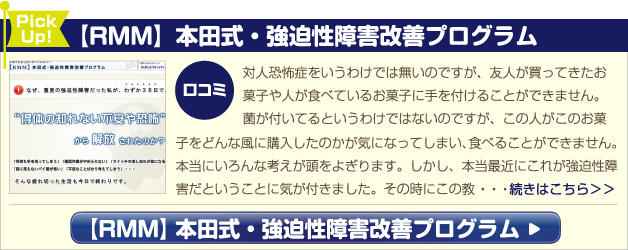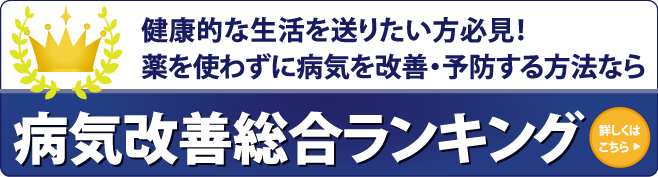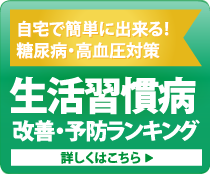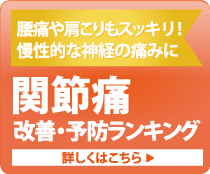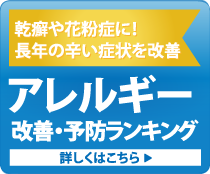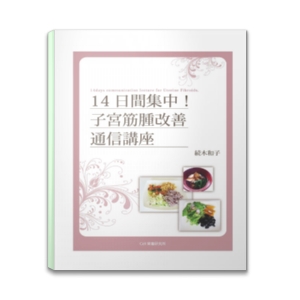子供の強迫性障害・小児の強迫神経症の症状の種類・症状の一覧
強迫性障害・強迫神経症は大人が悩まされているだけではなく、実は小児の子供も抱えてしまうことのある精神疾患ですが、悩まされている不安や恐怖はそれぞれで異なっています。
しかし、自分の子供が強迫性障害を抱えているということに気付かない親御さんもいます。それは、症状をなかなか把握することができないことや子供が症状を隠していることがあるからです。
そこで、早めにお子さんが抱える症状に気付き、改善策を取り入れるためにも、まずはどのような種類の症状が出るのかをチェックしておく必要があります。
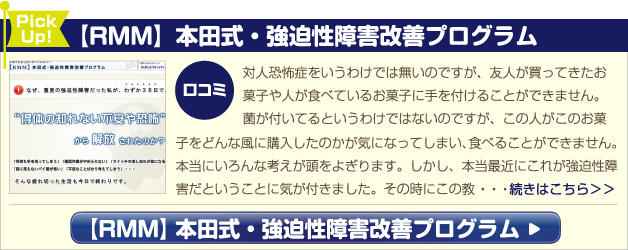
子供に強迫性障害・強迫神経症が発症するのはどんなとき?
強迫神経症・強迫神経症は、実は小児(2~15歳まで)の子供に発症しやすいものです。
その中でも、節目となりやすい10歳や小学校5、6年生になる頃に見られるようになります。この頃は身心が大きく発達する思春期でもあり周囲の目を意識することや自分自身を見つめることも多くなります。
すると、これまで僅かにあった強迫観念がしっかりと出てきてしまうことやそれを気にしてしまうようになることで、症状が表れやすくなります。さらに年齢を重ねていくと、大人になっても強迫観念や強迫行為の症状に悩まされてしまうのです。
これが発症してしまう原因は様々なものが関わっていますが、特に育った家庭の環境が一番大きく影響していると言えます。
厳しいしつけをする親であることや親が強迫性障害を抱えている場合、その影響によって子供も強迫性障害になってしまうことが出てきます。
子供がしつけを完璧に守るようになると「完璧にならなくてはいけない」と考えが生まれ、そこからどんどん逃げ道が無くなってしまい、自分自身を追い込んでしまいます。
大人の場合にはそういった環境でも、違う場所に行って息抜きをすることができますが、家や学校などの行き場が決められている子供にとっては、常に苦しさやストレスになって症状の慢性化に繋がってしまいます。
子供の強迫性障害・小児の強迫神経症の症状の種類・症状の一覧
小児の子供に見られる強迫性障害や強迫神経症には、「強迫観念」と「強迫行為」があります。
強迫観念とは、大人であれば「戸締りをしたか不安だ」などというあまり考えなくても良いものでも過剰に気にしすぎてしまうものです。また、強迫行為では強迫観念による不安を打ち消すためにとる行為ですが、過剰だと自覚していても、これを止めてしまうとさらに不安を感じてしまいます。
子供の場合には、遊びの内容や友達、親との関係、勉強中に起こることなどの範囲で強迫観念が出てしまうことやそれによる強迫行為が現れます。
本人にとっては、「決められた行動を取らなければ悪いことが起こってしまう」「こうしなくてはならない」などといった恐怖や不安を抱えていることがあります。
また、勉強中や人の話を聞いている最中でも集中力が続かず、すぐに手を止めてよそ見をしたり他のものに意識が向いてしまうことが見られます。
子供の抱える症状も、大人のように1人ひとりで異なり、100人いれば100通りの症状がありますので、「これが強迫性障害による症状かどうかわからない」ということもあります。
さらに、子供は自分自身で強迫観念や強迫行為が異常だと気づくと、親や周囲の人にばれないように隠すようにもなってしまいますので、親でも気づくことができないことがあるのです。
子供や小児の強迫性障害・強迫神経症を改善するには
子供や小児の場合、まだ成長過程でもあるため自然に改善できることもありますので、見守ってあげることも必要です。しかし、不安が多い場合には改善策を取り入れていくこともできます。
この症状を改善するには親が理解したうえでの協力が欠かせません。早いうちに症状を改善しておくことができれば、この先でも苦しむことは無くなるはずです。
そこで強迫性障害・強迫神経症の改善法の【RMM】本田式・強迫性障害改善プログラムが役立てられます。
この改善法を取り入れることで、得体の知れない不安や恐怖を抑えることができ、生活に支障を与えることや苦しむことも無くすことができるのです。
子供の抱える不安や恐怖を取り除き、より良い成長を考えているのでしたら【RMM】本田式・強迫性障害改善プログラムを取り入れることをおすすめします。